クルアーン
クルアーン
「コーラン」……Koran
「クルアーン」……Qur'an
ともに英語の音訳。最近はアラビア言語に近いQur'anが一般的になったことから日本でもクルアーンと書く傾向が強まっている。アラビア言語音では、どちらかというと「コラーン」に近いと主張する向きもある。
しかしアラビア語の表記には本来「ア、イ、ウ」の母音しかなく「エ、オ」は存在しないことから、より原語に近づけて発音すればコーランはクルアーンであり、メッカはマッカとなる。
啓示の言葉を誤解なく伝承するために、クルアーン朗誦はアラビア語で行わなければならない。近年まで他国語に翻訳することさえ禁じられていたほど、その厳格な姿勢は貫かれてきた。アラビア語はオリエント文明の担い手「セム民族」の言語に属しており、その中には「旧約聖書」が書かれたヘブライ語、イエスの語ったアラム語などがあり、アラビア語はそれらの言語と姉妹関係にある。
語源
クルアーンの語源に関しては諸説あり、
1.「誦むものである」……多くの学者が指示する定説
2.「誦まれるものである」……ヒリヤーニー学派の主張する受動態
3.「集めたもの」……ズジャージュ学派が唱えるが、少数派に属する
その他「結び併せたもの」「結合・接続したものである」、また、固有名詞として捉え、「旧約聖書(トーラー)」や「新約聖書(インジール)」同様、イスラームの経典に対して固有に付与された名称というイマーム・シャーフィー(イスラーム法学派の始祖)の説もある。
クルアーンの検証と吟味
クルアーンは神の啓示として、23年間、断続的にムハンマドに下された。切れ切れに下った啓示を正しく理解するために、後世の学者たちは、一つ一つの啓示がいつ、どのように下されたのか、その背景から内容を吟味していく。
預言者が当時どんな行動を取り、なにが語られ、側近に誰がいてどのように振る舞ったのか。残された口伝に誤りや虚偽の介在がないかを調べ、もちろん研究者による勝手な判断や推論の介入も、許されない。
研究手法の一例として、以下をあげる。
明けはなつ朝にかけて、静かに眠る夜にかけて、主は汝をお見すてたもうたのではない。憎んでおられるのでもない。汝には終わりのほうが始めよりどほどよいことか。主はきっといまに(たくさん恵みを)授けて、汝を喜ばせて下さろう──クルアーン第93章「朝」1-5節
この啓示には、それが下された原因が二つある。
【原因1】預言者が啓示のないところで悩んでいたとき、一人の女がきて「ムハンマドよ、お前の悪霊はどうしたのか、お前を見放したのだろう」と嘲笑した。それに対してこの啓示が降臨したという伝承である。
【原因2】預言者の家に野良犬の子がまぎれ込み、寝台の下で死んだ。預言者には四日間にわたり啓示が下されなかった。「預言者の家でなにが起こったのだろう。天使が訪問しないとは」との噂を聞いた次女が家を清めて掃除をしたところ、子犬を掃き出した。それで預言者への啓示が再開されたという。
以上の二つの原因の伝承者を調べると、前者がより正しく、後者は信頼性に欠けるため、第一の原因が採択された。
すべてにおいてこのように、調べ、吟味を重ねていく。
クルアーンと歩んだ初期イスラームの軌跡
イスラームの発祥
この聖典は眼で読むよりも、文句の意味を理解するよりも、何よりも先にまず声高く朗誦されなければならない。考えてみるともう一昔も前になるが、始めて本格的な「カーリウ(コーラン読み)」の朗誦を聴いた時、僕はやっとこの回教という宗教の秘密がつかめたような気さえしたものだ。オペラのマリアを歌うテノールかソプラノのような張りのある高い声、溢れる音量の魅力、一語一語の末までも沁み渡って行く、いかにもオリエンタルという名の連想にふさわしい深い哀愁の翳り。日常茶飯事を話題としてどことなく荘重で、悲劇的な色調をともすれば帯びやすいアラビア語こそ、こういう聖典には正にうってつけの言葉なのである。──岩波文庫『コーラン』上巻・井筒俊彦?訳、298〜299頁
クルアーンは基本的に押韻散文から成り立っているが、詩ではない。
当時のアラビア半島は「詩人の時代」「無道時代(ジャーヒリーヤ)」とも呼ばれ、沙漠を遊牧して暮らす部族中心主義のベドウィンたちは、その騎士道精神を高らかに詩に歌いあげた。部族間で抗争があった場合は戦場での勝敗にもまして自分の部族の勇猛さや高潔さをうたう詩が重要であり、それによって戦士を鼓舞した。優れた詩は口承でアラビア半島全体に広がり、作者は名をあげ、社会的にも大きな役割を果たし、敬意を払われる。
そんな優れた詩の様式を超える力を持つものとして、クルアーンは彼らに挑戦した。
騎士道精神を謳い、血のつながりを何より尊び、自らの豪傑さを愛したベドウィンも、部族間抗争で血の復讐を繰り返し、「悪に報いるには悪をもってせよ」というモラルのみで明け暮れる進歩のない日々にやがて疲弊し、人生の価値に疑問をいだいて精神的限界をむかえ始めた。彼らが最もおそれたものは存在の不安、すなわち「死の恐怖」。まさにそのタイミングでクルアーンは、鮮烈な「警告」の言葉を彼らに浴びせかけたことになる。
これ、よく聞け。この世の生活【いのち】はただ束の間の遊びごと、戯れごと、徒なる飾り。ただいたずらに(血筋)を誇り合い、かたみに財産の量と息子の数を競うだけのこと(*)。現世とは、雨降って緑の草が萌え、信仰なき者ども大喜び、と見るまに忽ち枯れ凋み、色褪せて、あとに残るはかさかさの藁屑ばかり。来世で待っているのは恐ろしい神罰ばかり──クルアーン57章、19節
(*)当時のアラブでは、男の子を持つことこそが生きがいと誇りであって、娘が生まれることはこの上もない恥辱とされ、女児は間引かれて生後すぐに生き埋めにされるなど、あからさまな男尊女卑が横行していた。
ジャーヒリーヤ
人生の価値への疑問、死の恐怖。人間にとってのそれら根源的な問題は、アッラーの教えを実践することによってのみ解消される。ここで大切なことは「実践」であり、実践する気のないものにイスラームの門戸は開かれない。イスラームとは「神への帰依」であり、神に帰依することを決めた人がムスリムと呼ばれる信徒である。
ジャーヒリーヤ=「無道時代」とは、多くの場合「無明時代(真の神を知らない無知の時代)」と邦訳されるが、その意味を考えると「無道」である方が語義的にしっくりとくる。イスラーム原理主義活動家サイイド・クトゥブの著書イスラーム原理主義の「道しるべ」によれば、世の中はイスラーム社会とジャーヒリーヤ社会とに二分され、ジャーヒリーヤの思考や様式は現代世界にもはびこって、人心を支配し、文化を汚染しているのだという。だから浄化が必要なのだと、人間は人間に隷属してはならず、あらゆる権威への隷従から解放され、アッラーのみに完全に帰依するべきだと説いている。
ジャーヒリーヤがそのような性質のものであるなら、イスラーム以前のアラブ社会は、まさに無道の時代。道なき不毛地帯に、浄化のための道しるべとなるクルアーンを置き、それを人々が実践することによって、「間違いのない社会」は成立する。
たしかにこのクルアーンは最も正しい道に人々を導く──クルアーン第17章9節
また、イスラームとは単なる理論ではなく、神の啓示をひとつひとつ、ゆっくりと実践することによって「生ける共同体」を創造していくという信仰であるのに、ジャーヒリーヤはムスリムたちに、「その信仰についてどれだけ研究したのか、どれだけの論文を出し、どれだけの主題について書いたのか。イスラームの法学性についての解釈は? 帰依を呼びかけている体系の詳細は?」と性急に問題を提起して彼らを困らせ、力をそらせ、信仰そのものを変質させようとする。
そんなジャーヒリーヤの思惑を見抜き、ムハンマド期のイスラーム共同体──初期ムスリムが実践していたアッラーの教え──を復興させ、我々を取り囲むジャーヒリーヤのあらゆる影響から、日々の生活を隔絶しなければならない。
これが、サイイド・クトゥブらによるイスラーム復興運動の、初期段階での呼びかけであった。
この項目に関しては、以下の評論も参照されたい。
イスラームと科学
ジャーヒリーヤを徹底的に排除しようと考えるサイイド・クトゥブは、哲学や心理学、倫理学などの学問分野はすべて、ジャーヒリーヤの信仰と伝統に影響されており、科学的分野においてもそれらが視野を思弁的な哲学の分野にまで広げた場合は信用ならないと言う。
たとえば生物進化論においてダーウィンは、生命の起源と真価を説明するための仮説を考案し、その仮説を表明するためだけになんの道理も証拠もなく科学的な観察の限界を超えて自らの欲望を表現した。物質的な世界において、進化論を正当化するために自然淘汰の構想を主張するなどあり得ないと憤慨する。
この進化論否定の思想はアメリカのプロテスタント原理主義者と共通する思想である。ヘブライ語聖書「創世記」第一章の「天の地創造」を信仰する彼らは、ミトコンドリアのような原生動物が生命体の起源であり、人類は猿人から派生したとする進化論を排斥する。と、訳者の注釈がついている。
なお人類の起源についてはクルアーンに明記されている。
誦め、「創造主なる主の御名において。人間を凝血から創りたもうた」──クルアーン第96章「凝血」1-5節
我は人間を創造するのに精選した泥を用いた。次にそれを精液の一滴として、しっかりした容器の中に納め、次いでその一滴を凝血(アラカ)に作り、次いでその凝血から、咀嚼状の塊(ムドガ)を作り、その塊から骨を作り、さらにその骨に肉を着せ、こうして新しい生き物を作り出した──クルアーン第23章「信仰者」12-14節
以上は、人間が「凝血」から作られたという科学的な啓示であり、近代まで解明されなかった胎生学の結論が、7世紀にムハンマドの口からすでに明示されていたとクルアーンの解説書(真実のイスラーム)にある。
最後の使徒
クルアーンは預言者ムハンマドが口述した神の意志を、弟子達がすべて暗記し、暗唱することによって広められた。ある日突然、神の意志が閃光のようにひらめいて、預言者の口から断片的にほとばしり出る。ムハンマドの身に起こったこの特異な現象を啓示という。
・予言者=未来に起こるであろうことを予知し、予見する能力のある人
・預言者=神から受けた啓示をただそのまま他の人々に告げ知らせる人
・使徒=特定の民族に遣わされ、その民族に神の啓示を伝えるという使命を負わされた預言者
上記に違いを示したように、イスラームを興したムハンマドはただの預言者ではなく、モーセやイエス同様、神の使徒である。ここで言う神は、民族・時代・宗派を問わずこの世にただ一人であり、アブラハムもノアもモーセもイエスもみな、唯一無二の人格神(アッラー)が時代ごとに遣わした預言者で、その最後を務めるのがムハンマドであるとクルアーンは説く。
汝(ムハンマド)以前に使徒を遣わし、啓示したのは、「我(アッラー)のほかに神はない、それ故に崇めよ」と──クルアーン第21章「預言者」25節
説け、アッラーは唯一神/永遠の神/子もなく父もなく/また双ぶべきものただ一つだになし──クルアーン 浄化の章
神の唯一性についてキリスト教がいうところの三位一体における「3」という数の概念は、イスラーム的にはあり得ない。唯一である以上「神の子」が存在できる余地はなく、天に「我らが父」は存在しない、つまり2も3もないという絶対的な唯一性がイスラームの特徴だ。
それがためにクルアーンは永遠不易の宗教と表現されるが、「永遠の宗教」が純粋な一神教として実現したのはアブラハム(イブラーヒーム)の時代であり、彼こそが絶対的一神教の精神を体現した預言者であるという考えにより、「アブラハムの宗教」とも呼ばれている。
また、神はけして人間の方から近づくことはできない遠い存在であるにもかかわらず、神の側からは人間にとてつもなく近い、たとえて言えば、
人間各自の頸の血管よりもっと近い──クルアーン50章、15節
そんな内在神でもあるという矛盾をはらんでいる。
人々は信仰を通じて、絶対超越神が突然限りなく親しい神として変貌するという人格的関係に入ることができるが、その関係は、人間を神の奴隷とし、すべてを神に委任して、なにがどうあろうと神の思いのままという絶対他力信仰的な立場に身を置くことによってのみ成立する。
このような神の存在自体の矛盾性に加えて、ムハンマドが人類最後の預言者であるというイスラームの考えは、後世、思想的な大問題を引き起こすこととなるし、ムハンマド自身、「クルアーンはのちのち、さまざまな混乱を招くことになるだろう」と弟子たちに予言している。
- ・思想的論争
- 一例として初期イスラーム神学で大論争を巻き起こした倫理問題があげられる。神と人間との関係において、もし人間がまったくの無力、無条件的な神の奴隷であるのなら、自由意志のない人間が悪事を働いた場合、それは人間の責任ではなく、すべては神の責任となってしまう。自分では悪を為す能力のない人間に悪事を強制しておきながら、これを罰するというのでは、神の正義が成り立たない。
- ・アッラー
- アッラーは、ムハンマドがどこかから勝手に持ち込んできた未知の神ではない。沙漠の古い神であり、カアバ聖殿に祀られている数百の偶像化された神々とは格式が違い、それら神々の中で至高の位置にあったことは、マッカの市民も認めていた。ただあまりに存在が遠いため、市民は身近で親しみやすい下位神を信仰し、アッラーのことを忘れていた。
マッカ期とメディナ期
ヒジュラ(聖遷)を境にして、マッカ期とメディナ期とではクルアーンの内容がガラリと変わる。
多神教で、偶像崇拝によって巡礼者から利益を得ていたマッカ(メッカ)のクライシュ族にとって、ムハンマドの説く純セム的な激烈さを持つ唯一神教は生活基盤を脅かす存在となった。
イスラーム発生以前、無道時代と呼ばれたアラブ地帯には、さまざまな部族(ベドウィン)が点在し、その部族ごとに固有の神が存在した。それぞれの神は偶像化され、マッカのカアバ聖殿に集められていた。カアバの起源については伝承しか残っておらず、それによればイブラーヒームがその息子イスマーイールとともに建立したことになっているが、そのカアバを管理していたのがムハンマドの属するクライシュ族だ。彼らがマッカに定住したのは五世紀半ばのことであり、先住者のフザーア族からカアバ聖殿の管理権を奪い取った。
カアバを管理しているという名誉を誇っていたクライシュ族は、その一族からひょっこり現れ、変な宗教を広めはじめたムハンマドという男の存在に、当初はとまどいを隠せなかった。いくら自分たちに不利益をもたらすとはいえ、ムハンマドはクライシュ族生粋の血筋を引く。なによりも血筋を重んじるクライシュ族にとって、その存在がやっかい以上のなにものでもなかったであろうことは容易に想像がつく。
- ・自由都市マッカ
- カアバ聖殿は巡礼の中心地であり、その威光のおかげでマッカはアラビア半島の諸部族から敬意を払われ攻撃の対象にはならなかった。シリア・イエメンのキャラバン中継地として商業も栄え、都市の統治は長老たちの合議によっておこなわれ、徴税もないという、冨と力のあるごく一部の者にとっては天国のように自由な都市であった。反面、もろもろの悪徳までもが自由に行われ、弱者は強者からの抑圧と迫害に耐えるしかない日々を送っていた。
マッカで虐げられている多くの弱者にとって、「唯一神アッラーの前に人はみな平等であり、アッラーにのみ服従するべきであって、人間の統治権は排除する」という神の啓示は、飢えた体に水が染み入るかのように、求め、欲していた教えであっただろうが、クライシュ族にとっては偶像崇拝の禁止、部族的モラルの無価値、祖先伝来の慣習の否定など、ムハンマドの口から出てくる言葉は神の名のもと、倨傲と背信に満ちたものばかり。
災いなるかな。他人の陰口をいう中傷者たちよ。お宝集めて銭勘定する者たち。その金が不老不死にすると思うのか。いやそうでない。砕【つぶ】し釜に必ず叩き込まれよう──クルアーン第104章「中傷者」1-4節
汝らは、祖先の歩んできた途が明らかに蒙昧頑愚の途であることを知りながら、しかもなお過去に執着することをやめないのか──井筒俊彦?「マホメット」27p
まことにこれは警告なり。自ら欲する者は(この警告を受け容れて)主への途をば選ぶべし──クルアーン第73章19節、第76章29節
ムハンマドとしては啓示の伝道こそが目的であって、けっしてクライシュ族を敵に回そうとは思っていなかったし、クライシュ族の中にもムハンマドを助け、保護する資産家が存在した。それ故にやり場を失ったムハンマドへの怒りは弱い立場のムスリムに向けられ、彼らへの迫害は次第にエスカレートしていく。ムハンマドは、命の危険にさらされたムスリムだけを順次市外へ逃避させた。
やがてムハンマド自身に暗殺の手が忍び寄る。危険を察知したムハンマドは、長年の盟友であるアブー・バクルただ一人を伴にして、夜陰にマッカから逃れ出た。行く先は、さまざまな理由からイスラームに入信する住民がすでに多数住んでいたメディナ(ヤスリブ)。
このメディナへの移住をヒジュラ(聖遷)といい、この年がイスラーム暦の元年(西暦622年)となる。
かくして「警告(タズキラ)」として威嚇、恐怖を前面に押し出したマッカ期のクルアーンは、メディナ期にはその基調を肯定的な「導き」に変え、現世への悪口はいっさい言わなくなった。台頭してヒジュラ後まもなく現れ出たのが、人々を戦闘へと駆り立てる、いわゆる「聖戦(ジハード)」の文言である。
戦いをしかけられた者たちには(戦闘が)許された。彼らは不義を受けたからである。まことにアッラーは、彼らを援助するに万能である。彼らは「私たちの主はアッラーです」と言っただけで、不当にも自分たちの家から追われた──クルアーン「巡礼章」39-40節(戦闘許可の節)
汝らに歯向かう者あらば、神の途において彼らを撃滅せよ。どこでも彼らを見つけ次第これに戦いを挑み、また彼らが汝らを追い出したところから逆に彼らを駆逐せよ。……氾濫が根絶し尽くされるまで、また全ての宗教がただ一つアッラーの宗教となるときまで敵と戦え──クルアーン第2章186-189節)
この激しさは、どうしたことか。
理由がある。ヒジュラによって、ムハンマドははじめてクライシュ族を「敵」だと認識したし、さらなる敵が移住先のメディナに存在することが判明した。ユダヤ人、それに続いてキリスト教徒である。
後世の我々は、その後8年間の戦いの末、ムハンマドがマッカを征服したことを知っている。だが夜陰にアブー・バクル一人を連れて故郷を追われたムハンマドや、その他大勢のムスリムたちには、その当時、異郷において、全く先が見えなかった。その心細さ、故郷への哀愁をおもんばかれば、いつかは故郷マッカに帰る──それはすなわち敵対するクライシュ族と戦って勝利すること──を、いかに渇望していたかが推察されよう。
その他、メディナ期のクルアーンの特徴として、比較的文章が長めで、啓示の内容が社会的になったことがあげられる。マッカでは一神教の原理を示すことが重要であったが、イスラーム国家が成立したメディナでは、信徒の生活を律する、より具体的な指示が必要であった。
アッラーの途に自分の財産を施す人を譬えれば、一粒に七穂をつけた種のよう、各穂には百個の粒がなろう。アッラーは御心にかなう者には倍加したまう。アッラーは広大で全知であられる──クルアーン第二章「牝牛」261節
みんなが汝に、月について質問してくるだろう。こう答えるがよい「それは人間(の便宜)のため、また巡礼のために定めたときである」と。それから、本当の敬虔とは、神を畏れかしこむ気持ちのこと。故にあなた方は表口から家に入るがよい。そしてアッラーを畏れなさい。そうすればあなた方もいまに栄ある人となるであろう。──クルアーン第二章「牝牛」189節
その後、最後の預言者といわれ、また、その妻のアーイシャをして「彼の本質はクルアーンだった」と言わしめたムハンマドが、自宅で息を引き取るまでの23年間、クルアーンはムハンマドの口を介し、ムスリムたちの記憶にとどめられ続けた。
言葉の力
沈みゆく星に誓って、汝らの友(ムハンマド)には迷妄も錯誤もない。己の欲望で語っているのでもない。それは、下された啓示にほかならない──クルアーン「星章」第1-4節
クルアーンには、自然を宗教的象徴として使った神秘的な章が多くある。月、太陽。暁や黎明、あるいは「諸星座のある天」。
七世紀当時のアラビア半島では、キャラバンは星を頼りに夜間に旅をした。人々の感覚は鋭敏であり、自然に対する優れた勘を身につけていた。加えて沙漠のベドウィンは、自分たちの詩の才能、言語的な審美眼を誇っている。クライシュ族も、クルアーンがアラビア語の韻文として優れたものであることを認めざるを得なかった。
40歳にして神の啓示を受けることとなるムハンマドは、そのずっと以前、キャラバンの一員として旅行中に、キリストの伝道師に巡り会う。そのとき彼らの口から発された流麗な文言の数々に、感心し、魅了されたというエピソードが残っている。
そんな経験も生かされたのか、ムハンマドの説くイスラームは、多少説得力に欠けるところを言葉の力で補っている傾向が強い。クルアーンの朗誦が、意味がわからなくとも心に響くのは、そういった、「音」の美しさや言葉の力があるからである。
禁酒の理由
アラビア地方はぶどうの産出地で、その汁が酒に変化するのは当たり前の現象であり、オアシスではなつめやしが発酵してやし酒となる。気分を高揚させ、あるいは恐怖を麻痺させるものとして、この地方では古くから祭りや戦闘時に酒は欠かせないものだった。だが乾燥気候で飲酒をすると血中のアルコール濃度が急激に高まるし、酔い覚めに飲む大量の水は、沙漠地帯ではあまりにも貴重だ。なにより酩酊時に敵に襲われたらひとたまりもない。
ところが、やめろと言われてやめられるものではないのも飲酒の習慣だ。そこで、ある啓示が下される。
これ、信者のものよ、酔うているときには、祈りに近づいてはならない。自分の言うことがはっきりわかるようになるまで──クルアーン 第4章「女性」43節
つまり酔っているときには礼拝するなという戒めなのだが、一日五回の礼拝が定着していたその頃では、礼拝と礼拝の感覚が短いため、日中に飲酒をすると酔いを醒ますひまがない。この戒めの効果は抜群で、飲酒はかなり減ったという。そのように段階を踏んで人々が徐々に禁酒に慣れたころ、飲酒は罪との烙印がきっぱりと押され、以後は全面禁止となる。
クルアーンの啓示が社会を変革させるための律法を含んでいるということを如実に示すエピソードだ。
滅びの日
しかしながら、意味が曖昧であり、いかようにも解釈できるクルアーンには、内在する問題点があると、初期の頃から指摘されてきた。その上クルアーンは、アラビア語原典で読まなければならない。この点が、時代や地域を超えての論争や紛糾に拍車をかけた。
自分の死後、そうなるであろうことをムハンマドが予測していたことはすでに述べた通りだが、その懸念が、以下の啓示にも表れている。
アッラーこそは、汝ムハンマドにこの聖典を下されたお方、その中には文言が明快なムフカム諸説があり、それが聖典の母体である。それから別に文義が曖昧なムタシャービフとがあり、心に邪曲を持つ者たちは、その文義曖昧な方に取り付き、それをもとに騒動を企てたり、また自分勝手な解釈をしようとする。だが本当の解釈はアッラーのみが知ること。確固とした知識を持つ人々は言う。「私どもはクルアーンを信じます。すべては我らの主の御許から来たもの」ただ思慮ある人々しか反省しない──クルアーン第三章「イムラーン家族」7節
学者たちは、この節を素直に受けとめ、正しい解釈は神のみぞ知るとして、信徒からの質問には「我々は信じるのみ。すべては主の御許から」と答えていた。永遠に答えの出ない宗教。それこそがイスラームの魅力であり、残酷さでもあるのだろう。
滅びの日、人々は、正しくあるために。ただそれだけを祈って『行い』(*)の日々を過ごす。その日自分が、アッラーの御許に召される者であらんことを。
慈愛あまねき、慈悲深い、アッラーの御名において
讃美あれ、アッラーに、よろず世の主、
慈愛あまねき、慈悲深い、お方
裁きの日の主宰者、
あなたにのみ、われらは仕え、
あなたにのみ、助けを請い願う
真っ直ぐな正しい道へ、われらを導き給え。
あなたが恵みを与え給う者の道へ
あなたのお怒りを受ける者でなく、
まどいさまよう者でもなく。
──クルアーン第一章「開扉」 鈴木絋司 訳
(*)『行い』の中にジハード(聖戦)が含まれていることについては、ムハンマドの項に改めたい。
 コーラン 上 岩波文庫 青 813-1
コーラン 上 岩波文庫 青 813-1 コーラン〈中〉 (岩波文庫)
コーラン〈中〉 (岩波文庫)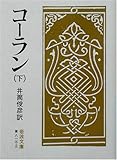 コーラン 下 岩波文庫 青 813-3
コーラン 下 岩波文庫 青 813-3 真実のイスラーム―聖典『コーラン』がわかれば、イスラーム世界がわかる(鈴木 紘司)
真実のイスラーム―聖典『コーラン』がわかれば、イスラーム世界がわかる(鈴木 紘司) 『クルアーン』―語りかけるイスラーム (書物誕生―あたらしい古典入門)(小杉 泰)
『クルアーン』―語りかけるイスラーム (書物誕生―あたらしい古典入門)(小杉 泰)
Keyword(s):
References:[ムハンマド] [真実のイスラーム] [シーア派] [イスラーム] [シーア派イスラーム] [イスラーム原理主義の「道しるべ」]